 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
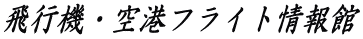
 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
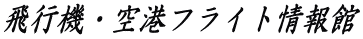
日本航空機開発協会によれば、2006年末に全世界で民間のジェット旅客・貨物輸送機は約1万4700機が運航している。航空運送サービスの費用に最大の影響を与える要素は航空機である。
(路線)需要に対して投入する航空機の大きさ(規模)、航続距離、速度(ただしジェット機では差異はほとんどない)について運航に関する費用は影響を強く受ける。このため需要の大きさにマッチした航空機を投入していくことが原則になるが、航空機には機材の規模が大きくなるほど単位当たり(座席キロ、有効トンキロ当たり)の運航費用が低下する、いわゆる規模の経済性が働くという特性がある。
ドガニスは航空機の機材規模に経済性が働く理由を2つあげている。1つは、機材は大型化すると抗力(空気の流れの速度方向に平行で逆向きの成分)が低下し機材重量単位当たりの搭載量が増加すること、もう1つは各種技術の発展で100席機材も500席機材も双発のエンジンで運航され、整備費用は5倍にはならないことをはじめその他の各種費用も大型航空機になるほど費用増加率は逓減していくことである。
航空機は区間距離の経済性も働く。これは同じ型式の航空機を使っていても平均区間距離が長いほど費用総額の伸びは小さく座席キロ当たりなど単位生産量当たりの費用は逓減していくことである。理由は航空機の燃料消費量は離陸~上昇中・下降~着陸までが大きく上空巡航中が最小になる。また空港滞在時間では貨物旅客の搭載取り降ろしの各種費用が発生するなど、長距離区間路線ほど巡航部分が増加するため、各種費用の増加率が逓減するからである。
大型ジェット機の座席キロ当たり運航費用は、同じ区間の小型ジェット機の座席キロ当たり運航費用に比較すれば低くなるが、1便当たりの運航費用は大型ジェット機のほうが高くなる。このため航空会社は運航が予想される路線の需要規模や運航のパターン、空港の諸条件(滑走路長やその他運航への支障の有無)などを十分考えて機種や導入数を決める必要がある。
各航空機は機種ごとに最大離陸重量が定められており、最大離陸重量は航空機自体の運航時のカラ自重(機体重量や機用品重量など)に燃料と有償搭載量(旅客・貨物など)の組み合わせで計算される。最大の有償搭載量を載せて最大離陸重量で離陸する場合の航続距離を最大有償搭載時航続距離という。
この距離を超えて飛行するためには、最大離陸重量の範囲内で離陸するため、最大であった有償搭載量を一部削り、代わりに燃料を搭載し機体の燃料タンクを満杯にして航続距離を延ばすことができる。このときの搭載量が最大航続距離搭載量である。燃料タンクが満杯の状態で有償荷重の搭載量を減らしていけば、その分重量が軽くなるので運航可能距離はわずかに延びる。
航空機の生産量は輸送量×輸送距離で表される。ドガニスは航空機にとって最大有償搭載時航続距離までの距離範囲内で最大有償搭載時航続距離に近い距離帯が同じ費用で最大距離を運べるため単位当たり費用が最低水準に近くなることから、その航空機にとっての最適な航続距離であるとしている。
スピードを求めた時代