 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
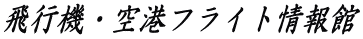
 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
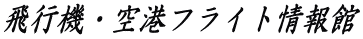
一般に戦闘機の総合性能の優劣を語る場合、エンジン出力が大きい方が最終的には優れた結果を残すことがほとんどである。しかし出力は無限に大きくすることは不可能であり、それが限界に達した場合、機体の軽量化によってバランスを取る必要が出てくる。
太平洋戦争勃発時、日本陸海軍航空隊が配備していた一式戦闘機と、零式艦上戦闘機は、いずれも1000hpクラスのエンジンを搭載するにとどまっていたが、米英軍の戦闘機を総合性能で圧倒した。それは機体が軽量ゆえに、水平面での運動性能(旋同性能)と上昇力に優れていたことが理由である。どのくらい軽量だったかというと、年一型の1580kg、零戦二一型の1680kgという自重は、同時代の他国の代表的な戦闘機、たとえばアメリカ海軍のグラマンF4FやカーチスP-40などより1000kg前後も軽かった。
こうした軽量化は、軍からの過酷な要求ゆえだったのだが、それでも開発側は機体のあらゆる場所に重量軽減穴を開けるなどしてこれを達成した。しかしその結果、機体強度に劣るという欠点が表面化したため、上昇力に優れていた一方で、その反対の急降下性能、そして機体に最も大きな負担(G)がかかる急降下からの引き起こしに際し、制限を受けることを余儀なくされた。
ちなみに太平洋戦争の勃発からしばらく経ってから、隼や零戦に追われた連合国軍戦闘機は、急降下によって攻撃を回避するという戦法を編み出すが、そのきっかけとなったのは、捕獲機を通じて行われた性能検証の結果である。そこでは、自国の戦闘機とさほど変わらぬ機体サイズにもかかわらず、前述の通り比較にならないほど軽量だったことに驚かされた、というレポートが記録されている。
一方、戦いが進むに従って、機体の改修と装備の充実化が実施された一式戦闘機と零戦は、いずれも後期型では初期型に対して500kg前後も自重が増すこととなった。このことは初期型の特徴でもあった優れた運動性能を失ったことを意味しており、効果的なエンジンのパワーアップがすでに限界に達していたこともあり、その性能はジリ貧にならざるをえなかった。
対して最初から過激な重量軽減策よりも機体強度の確保を重視していた陸軍航空隊の三式戦闘機「飛燕」や、四式戦闘機「疾風」などは、いずれも隼の初期型より1000kg以上重かったものの、最初からその重さなりの戦法で運用されたこともあり、戦闘機として一定の評価を得ている。この2機はエンジンのトラブルの多さのために、その性能にはマイナス評価が付く場合も少なくないのだが、それはまた別の問題である。
いずれにしても、太平洋戦争末期になると敵味方いずれも重い機体を大馬力のエンジンで引っ張り、上昇力よりは急降下性能を、水平面ではなく垂直面、すなわち縦の機動に依存するといった戦い方が主となっていった。これはヨーロッパ戦線も同じだった。