 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
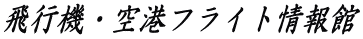
 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
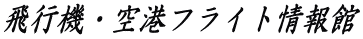
目次

2.
さて、次は諸外国の戦闘機である。まずイギリス空軍の場合、製造メーカーに一任されていた。有名な「スピットファイア」の意味はスラングに由来する「性悪女」、その後継機たるスパイトフルは「悪意」、その艦上機型のシーファングは「海の牙」といった具合に統一性はまったくなく、相当にくだけたネーミングだった。
一方アメリカだが、こちらも軍自体に制式番号以外のネーミング基準は存在せず、メーカーに一任されていた点はイギリスと同じだった。たとえばカーチス社の機体は「ホーク」「ウォーホーク」「トマホーク」といった具合に一定の統一性があったが、ホークが鳥のタカだったのに対して、 トマホークは鳥ではなくネイテイブアメリカンが使っていた投げ斧であり、単なる文字列での統一だった。
ベル社の場合は、コブラに関するものを使っていたものの、P-39「エアラコブラ」(空のコブラ)が架空の生き物だったのに対して、P-63「キングコブラ」は実在のコブラの種類だった。海軍航空隊の場合はグラマン製の機体が「ワイルドキャット」から始まり、「ヘルキャット」「タイガーキャット」「ベアキャット」と猫シリーズで統一されており、この流れは戦後も継続され最終はかの「トムキャット」だった。
ドイツの場合は、基本的にメーカーの制式番号のみであり、一部に制式番号の一部のアルファベットを取って、メッサーシュミットBf109のE型を「エミール」、F型を「フリッツ」、G型を「グスタフ」といった具合に、識別名称に使っていた例はあった。
この他イタリアなどは、マッキMC200が「サエッタ」(矢)、MC202が「フォルゴーレ」(稲妻)、MC205が「ヴェルトロ」(グレイハウンド大)といった具合に、統一性はまったく無かった。ソ連は戦闘機の制式番号は当初は数字だったのが、途中からメーカーの略称+数字(Yak-9やMiG-3など)と変わり、愛称的なものは基本的にはなかった。