 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
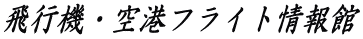
 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
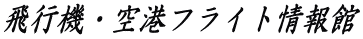

2.YS―11の胴体下、ワイヤーアンテナ
HF無線機は、見通し範囲を越えた距離での通信に使われる。したがって737のように国内線を主に飛ぶような旅客機には装備されていない。
ところが同じく国内線で活躍した国産旅客機YS-11の古い写真を見ると、胴体の下などにHF無線機のワイヤーアンテナを確認できる。どうしてYS―11に長距離通信用のHFアンテナが装備されていたのだろうか。
たとえば那覇空港で撮影した南西航空(現JTA)のYS-11だが、胴体下にツノのように支柱を伸ばしているのが見える。ワイヤーアンテナは、この支柱の先端を結ぶように張られている。洋上飛行の多い南西航空ではHF無線機が必要なのかと思うかもしれないが、それにしては現在のJTA機にはHF無線機は装備されていない。
新千歳空港で撮影したエアーニッポン(現ANA)のYS‐ 11だが、やはり胴体下にHFアンテナがついている。同社は主にANAから委譲された地方路線を運航していたが、日本本土にもVHFが届かないエリアがあったのだろうか。
そこで音を知る整備士OBに話を聞いたことがあるのだが少なくとも戦後の日本では(つまり現代と同じような航空管制が一般化してからは)、最初から飛行場管制やエンルート管制にはVHFが使われており、また国内ではVHFが届かない場所はなかったという。
しかしYS-11はHF無線機を票準装備していた。それはYS-11が国内だけでなく広く海外に輸出することを狙った旅客機であり、そのためにはHFを標準装備とした方が有利だと判断されたためらしい。海外には、まだVHF通信網が十分に整理されていないエリアも少なくなかったのだろう。
そこで日本の航空会社が導入した機体にもHFアンテナが装備されていたが実際には使わないのに整備の手間や費用はかかってしまう。しかもこうしたアンテナは飛行中に被雷してダメージを受けやすい。つまり必要のないHFアンテナはついていない方がマシということで改修プログラムが策定され、順次HFアンテナが撤去されていった。だから特に退役近くに撮影されたYS‐ 11の写真では、HFアンテナがついていないものが多いのである。