 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
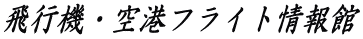
 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
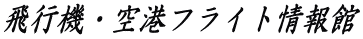
目次
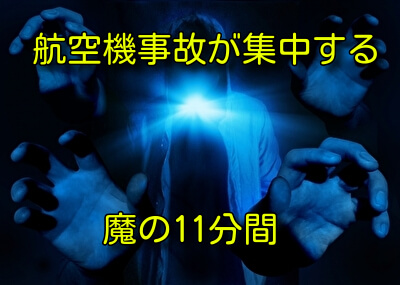
航空機の事故は、離陸後の3分間と着陸前の8分間に集中しており、「魔の11分間」といわれています。
原因としては、ダウンバーストなどの突然の環境変化や人為的ミスにあると考えられています。
離着陸はパイロットにもストレス
「クリティカル・イレブン・ミニッツ」という航空業界の慣例用語の日本語訳が「魔の11分間」です。
この言葉が表すように、世界中の航空機事故の約7割が、離陸後の3分間と着陸前の8分間に集中していることから、離着陸時の危険度の高さを表現する言葉として用いられています。理由はいろいろと考えられますが、離着陸時は自動操縦ではなくパイロットが手動操縦していることも、その要因といえるでしょう。離着陸時の際、パイロットには、操縦以外にチェックシートに基づいた様々な作業が義務付けられています。また、計器やエンジンチェックとは別に、離着陸の指示を仰ぐために管制官との交信も頻繁に行う必要があり、この作業に忙殺されることで、緊張度が高まるともいわれています。
このようなストレス状態を維持しながらの作業が続くわけですから、人為的なミスの発生率も高くなり、パイロットとしては最も注意が必要な時間です。
では、離陸と着陸ではどちらが難しいのでしょうか。
操縦技術の面では、安全に高度をゼロにする着陸だそうですが、総合的に考えると離陸が難しいといわれます。その大きな要因は、離陸時は航空機が持ち得る最大のパワーを出し切っている状態が続くことにあります。つまり、航空機にとって余裕がない状態であり、トラブルに対しても瞬時の判断が事故の大きさを大きく左右します。
したがって、離陸の取りやめは最大パワーから急激に低下させることになり、オーバーランを引き起こしやすいといわれています。
ダウンバーストの発見者は日本人
離陸時と比べて着陸時は、徐々にパワーダウンさせていくので、航空機にパワーの面で余裕があります。
このため、着陸のやり直しが必要な場合でも、急激なパワーアップに対応できます。
しかし、怖いのは空港近辺で発生するダウンバーストと呼ばれる強力な下降気流です。高度を下げてきた航空機に対してこの下降気流が作用すると、空気のかたまりを押し付けられたようになり、急激な落下に巻き込まれて、墜落の可能性もあります。
現在は、ダウンバーストを観測するため、空港にはドップラー・レーダーが設置されていますので、従来に比べれば危険性は低くなったといえるでしょう。
実はこのダウンバーストをはじめて発見したのは、竜巻研究の第一人者で、竜巻の大きさを表す「Fスケール」でも有名な気象学者の藤田哲也博士です。