 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
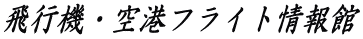
 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
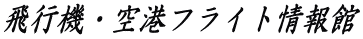
目次
2.どこへ就職すればいいの?
グランドハンドリング会社へ入社
ここで紹介するグランドハンドリング業務には、航空会社に就職しなければつけない仕事と、航空会社の関連会社に就職することによってつける仕事とがある。前者は、総合職のメカニック、後者はメカニックとその他のグランドハンドリングの仕事である。つまりメカニックは、航空会社の社員として働く方法と、関連会社の社員として働くという両方の方法があるということである。
また、職種によっては、企業が雇ったアルバイトが主体となって業務をこなしている仕事もある。たとえば、機内清掃、機体清掃、貨物の積み降ろしなどがそれだ。
航空会社の社員として働く職種はたいてい総合職や一般事務職として新卒で採用され、配属される。航空会社の関連会社で行っている職種は新卒、中途の両方の採用方法がある。アルバイトを採用する場合は、アルバイト情報誌や就職情報誌を利用して募集を行っているケースが多い。
体力勝負の仕事場
最近は女性も活躍
グランドハンドリングは、ランプ(空港の制限区域内)が仕事場だ。真夏の炎天下あるいは風や雨、雪という悪天候の中での仕事なので体力勝負。そのため、これまでは男性の職業というイメージが強かったが、機械化が進んだこともあり、最近では女性の活躍もめざましい。例えば、成田空港の新東京空港事業(株)や羽田空港の国際空港事業(株)では、女性を積極的に採用している。
3.
ランプコーディネーター
在、ランプコーディネーターは、航空会社の一般職か、あるいはグランドハンドリングを委託している関連企業の職員が担当している。
航空会社の場合は、通常、入社の時点において配属が決定し、一定期間の社内研修を経て、社内試験を受けることになる。
合格すると、現場においてOJT(実際に仕事をしながら研修していく)を行い、正式なランプコーディネーターとして働くことになる。
メカニックのような国家試験はないものの、社内の専門のチェックを受けるという点では、専門職といえる。
近年、ランプコーディネーターという職種を廃止する航空会社もあり、今後はその業務自体が関連企業に移されるケースが増えていく傾向にある。
まずはグランドハンドリングの関連企業に入社し、経験を積んでランプコーディネーターになるのが近道だろう。
機内清掃
航空機に乗ると、いつも機内はきれいに整理されている。当然のことのようだが、これは機内清掃のスタッフが、短時間のうちにまっさらな状態に整えているからである。
機内清掃スタッフの仕事は客室の掃除機かけ、シートカバー、まくらカバーの交換、ごみの回収、トイレの清掃、新しい備品の設置などであるが、目的地に到着後、折り返して次の使として出発する飛行機などは、わずかなプラントスティ(通常、30~60分)の間にこれらのことをこなすので、時間が勝負といわれる仕事でもある。機内清掃のみならず、降機した乗客から忘れ物の届けがあった場合、機内清掃中に見つかればいいが、見つからない場合は機内に戻り、ときには捨ててしまったゴミまでチェックすることも。
快適な機内を提供するためには、こうした影の業務が必要不可欠なのだ。
一方、空港でランプを眺めると、たくさんの航空機が美しい機体を輝かせて待機しているのを見かける。機体には、それぞれの航空会社の塗装がほどこされ、さまざまな塗装を眺めるだけでも楽しい。このように見るものの目を楽しませてくれるのは、機体を清掃している職員のおかげだ。航空機は航空会社によって異なるが、約40日ごとに清掃される。機体を美しさを維持するばかりでなく、腐食防止のためにも、機体清掃を欠かすことができない。
日本航空が自動クリーニングシステムで清掃しているが、その他のエアラインでは人がモップを持って機体を手で清掃する。
何人もの人が航空機に張り付くのだ。清掃は夜の間に行われる。
機体清掃や機内清掃などの業務は、航空会社の関連のグランドハンドリング会社がたいてい行っている。これらの企業で、機体・機内清掃や貨物の積み降ろしに正社員や契約社員を配属することもあるが、現場ではアルバイトが活躍する分野である。
マーシャリング業務
大型機のマーシャリングには、マーシャリングカーを使用する。パイロットから視認しやすい高さにマーシャラーがスタンバイするため、ボーイング747ではかなりの高所作業となる。巨大な航空機をパドルだけを使い、ピンポイントに誘導していくが、このとき左右の翼端には監視者が立ち、連携して安全を確認しながら作業にあたる。
基本的なマーシャリング動作について解説しよう。
彼らが乗るマーシャリングカーの台の高さは、最高で約4メートル。雨の日も風の日もしっかりと足をふんばって、向かってくる旅客機に正確な合図を送らなければならない。
まずはパドルを持った両腕を上げる。これは「注目せよ、スポット誘導を開始する」という合図だ。そして上げた両腕の肘から先を内側に曲げ伸ばし。すると、今度は「そのまま直進せよ」の意味に。右手で斜め下の方向を指し示し、斜め上に上げた左腕の肘から先を内側に振ると「左へ」。反対は「右へ」の合図になる。
「速度を落とせ」という指示は、開き気味に下げた両腕を肩を起点に上下に振ればOK。そして「停止」させるときは、上げた両腕を頭上で交差させて合図を送るのである。
以上はマーシャリングの基本的動作の一例だが、さまざまな動作を間違いなく現場で実践できるようになるためには相当な訓練が必要だ。
空港というと男性の職場のようにも思えるが、近年は女性の進出も目立ち、多くの女性マーシャラーが各地の空港を舞台に活躍している。
ところで最近、大都市の空港である異変に気づいた。マーシャラーが見当たらない。赤外線レーザーで旅客機の位置を測定し、誘導するVDGS(visual docking guidance system)の運用がはじまっているのだ。
到着機はVDGSのLED表示部に示される現在位置と停止位置までの残距離をもとに、前輪が地面に引かれているライン上をきれいにトレースし、所定の位置まで進んで静かに停止する。現代のハイテクが空港のこんなシーンでも活躍していることに感心する。
トーイング業務
トーバーを使用しないニュータイプのトーイングカー。U字型の車両の中心部にあるビックアップ装置で、航空機のノーズギアを持ち上げて肇引する。最大出力は515馬力で、ボーイング777なら時速30キロでトーイング走行可能。運転席には前向きと後ろ向きにハンドルがあり、シートが回転する。
プッシュバック業務
航空機のノーズギアとトーイングカーをトーバーで接続し、自力でパックできない航空機を所定の位置まで押し出していく。このとき乗客を乗せた航空機のすべてが委ねられる。
その名の通りバックで走行するため、ステアリング操作は非常に難しく、グランドハンドリング業務の中でも、最も経験が必要とされる作業のひとつ。
チョークマン業務
所定の位置に停止した航空機のノーズギアの各タイヤの前後にタイヤチョーク(車止め)を装着する。
もちろん航空機にもブレーキがあるが、万全を期している。乗客の搭乗や、貨物の搭載によって、重量により機体が沈み込むので、タイヤチョークで装着する。到着時のチョークオンに対して出発の際にタイヤチョークを外すことをチョークオフという。
パッセンジャーステップ着脱業務
パッセンジャーボーディングブリッジのないスポットヘ航空機が到着した場合、乗客の乗り降りに使用される車両。タラップ車とも呼ばれる。シップサイドに止め、事前に航空機の客室床の高さに設定し、航空機に装着してからアウトリガーを張り出す。ステップを動かす操作パネルは、ステップ前方に設置されている。車両を運転するには大型免許やパッセンジャーステップ車の作業資格、航空機のドア操作の資格が必要になる。
貨物の積み下ろし
空港スタッフとして航空貨物輸送業務で働こうの項目で詳しく紹介しています。
航空整備士
空港スタッフとして航空機の機体整備士で働こうの項目で詳しく紹介しています。
ケータリング
機内食の調理から搭載までを担当。
旅の楽しみといえば、機内食。とりわけ競争力が激しい国際線では、航空会社は、機内食にあの手この手の工夫をこらす。
機内食は、航空会社が独自に工場を持って作るのではなく、航空会社に委託された機内食(ケータリング) 会社が担当している。日本の場合、自社の関連会社が請け負って行っている場合が多い。
多くの航空会社の機内食を請け負っているケータリング会社になると、何と数万食以上にものぼるという。
ジャンボジェット機クラスが満席になると、300人分以上もの機内食を搭載することになる。ファーストクラス、ビジネスクラス、エコノミークラスそれぞれのクラスごとの食事というふうに種類もさまざま、その量も膨大なものになる、料理は熱を通すだけの調理された状態で航空機に搭載され、客室乗務員が加熱して乗客にサービスされる。
JAL系ケータリング会社で毎年新卒者を採用
機内食を作るケータリング会社のスタッフは大きくわけると、調理師を始めとする調理部門のほかに、管理部門、受注部門、機内食のメニューを企画する部門、搭載部門、補給部門などがある。
大手のケータリング企業になると、新卒も中途採用も行っているが、中小規模の企業は、欠員が出た場合の中途採用が主体。そんななかJAL系の(株)ティエフケーは、毎年一般の専門学校、短大、4年制大学の新卒者を採用している。調理師免許も必要ない。
ケータリング会社のスタッフは、機内食の搬入や撤去のときに、各航空会社の客室乗務員とやりとりすることが多い。外国航空会社のケータリングを受託しているケータリング会社では、英検2級程度の英語力が求められる。
インフォメーション業務
空港スタッフとしてインフォメーション業務で働こうの項目で詳しく紹介しています。
貨物カウンター
空港スタッフとして航空貨物輸送業務で働こうの項目で詳しく紹介しています。
通関士
海外からの到着・輸出貨物の通関を迅速に手配
Q 通関士って、どんな仕事をするの?
日本に持ち込まれる製品にはすべて関税がかけられるが、製品ごとに関税率が異なる。貨物の受収人は、送られてきた貨物をみて、税関用の書類を作成する。この書類は、海外の貨物を日本向けの貨物にするためのもの。日本から海外に貨物を送る時も、同様の書類を作成する必要がある。このように税関のチェックを受けることを通関といい、通関の手続きを輸出入業者に代わって行う人を通関士という。
Q 通関士の働く場所は空港だけなの?
年々海外から航空便で送られてくる貨物は増えてはいるものの、通関士の勤務場所は必ずしも空港内でない場合がある。たとえば、成田空港に到着する貨物の場合、ニュースフィルム、動物、植物、生鮮食品などのナマモノや大使館の荷物以外は、成田空港から47キロ離れた市川にある東京エアカーゴ・シティ・ターミナル(TACT)に送られる。ここの勤務になる通関士も多い。
Q どうすれば通関士になれるの?
通関士になるためには、ふたつの条件をクリアしなければならない。資格をとることと、通関を行う会社に人社することである。
国家資格を持ち、通関業を行っている会社に入社して初めて通関士となれる。
学生でも受験することができる国家資格を収得しておけば、通関業の会社に就職活動をする場合に有利。国家試験は、年に一度行われ、施され、通関業法、関税法・関税定率法・その他関税に関する法律(関税暫定措置法、外為法など)
の4つの法律に関する知識及び通関実務に関する知識が問われる