 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
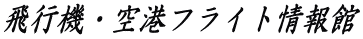
 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
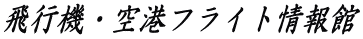
目次
日本にしかるべき競争環境を実現するためには、世界的に見ても高い空港使用料や航空機燃料税といった公租公課を引き下げる必要があります。これに足を引っ張られていては、外国の航空会社とまともに競争することができないからです。
公租公課の引き下げに最も有効なのは、空港に関する政策を根本的に見直し、空港の経営を民営化することです。空港に関わる施設を一括管理する形で民営化すれば、経営責任や各空港の個別の採算性も明確になりますし、より機動的な空港運営が実現できると思われます。
すでにヨーロッパでは空港の民営化は進んでいます。空港への投資が国境を越えて行われていますし、複数の空港の一体的管理も国際的に実施されています。
一方、日本の航空法は、空港に対する外資の出資を制限しています。これについては、羽田の空港ビルにオーストラリアの投資会社が投資をした際、大きな議論を呼びました。空港は、戦争などが起こった場合、即時に軍事のために使用されなければならないため、常時日本人の経営主体によって運営されているべきだと強く主張されたのです。
しかし、ただ頑なに外資の参入を敵視するのではなく、「何が問題なのか?」
「どのようにすれば軍事上の緊急時に対応できるか?」ということにまで踏み込んだ議論が日本でも必要になってきています。
また、現実に空港を民営化していく際には、暫定的な措置として、「指定管理者制度」のようなシステムを導入していくことも考えられます。
指定管理者制度というのは、施設の運営を外部の業者に委託するシステムで、現在は博物館などで取り入れられている仕組みです。ノウハウのある専門業者に入ってもらうことで、より効率的に施設を運営することを狙いとしています。
すでに名古屋空港(小牧空港)で導入されていますが、他の空港でもこうしたシステムによって運用効率を高めれば、その利益は地元にもさまざまな形で還元されますし、航空会社の負担も減り、その空港が航空会社によって選ばれやすくなるという好循環が形成されることになります。
逆に、経営努力を怠る空港は淘汰される時代が本格的にやってきます。これまでは、航空会社にある程度の余裕があった上、行政の強制力が働いてきたこともあって、どの空港も「安泰」でした。
しかし、国際競争が激化し、航空会社も本格的なリストラを断行しなければならない現状においては、航空機が1便も飛ばない空港が出てくる可能性すらあります。当然ながら、そのような空港は廃港になるしかないでしょう。
手続き上、空港を廃港にするのはそれほど難しいことではありません。採算が立つ見込みもない空港をいつまでも抱えて赤字を垂れ流し続けるのか、それとも、早めに廃港を決定して新たに転用する活路を見いだすのか、経営難の地方空港を抱える地方自治体には、まさに今こうした選択が突きつけられているのです。