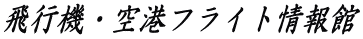シカゴ条約で定められた航空輸送の形態は9段階あり、それぞれに認められる自由の範囲が規定されている。「自国」の航空機が、「相手国」や「第三国」において、どこまでの行動が認められているのかが、航空輸送の自由の具体的な中身である。
たとえば、「自国」が日本、「相手国」と「第三国」が韓国もしくは中国だとしよう。この場合の「自国」の航空機とは、日本国籍をもつ航空機である。この航空機が韓国や中国において、どこまで自由に振る舞うことを認めるのかが問題となる。
まず、第1の自由は、「相手国」の領域を「自国」の航空機が無着陸で横断飛行できる権利である。そして、第2の自由の範囲では、「相手国」に給油などの目的で着陸できるが、貨客(貨物と旅客)を降ろすことはできない。「相手国」にて貨客を降ろす自由は、第3の自由の範晴である。
シカゴ体制のもとでは、第1の自由と第2の自由が各国に与えられた。しかし、第3以降の自由については、「自国」と「相手国」による2国間の協定で認められるものとされた。
オープンスカイ政策とは2国間協定による航空の規制緩和であるが、アメリカはオープンスカイで第6の自由まで認めている。また、EU域内のオープンスカイと、英国とシンガポール国間のみが、究極の自由である第9の自由を認めている。これは、「自国」の航空機が、「相手国」の国内で輸送することができる自由であり、カボタージュと呼ばれている。これら以外の国では、カボタージュは規制されている。
一方、民間航空の運営に必要となる運賃などの商業的な取り決めについては、シカゴの会議では何も規定されなかった。そのため、航空会社が独自で国際航空運送協会(IATA)という業界団体を設立し、運賃調整を行うことになった。
IATAの運賃調整会議の議決は全会一致でなされ、決定に従って運賃が決められた。それに対して欧米の政府は、IATAがカルテル(企業間で価格や生産量などを協定すること)であると長らく非難してきた。航空の自由化が進むなか、IATAの運賃調整に従わない航空会社も出てきた。2006年、EU委員会がIATA協定を段階的に違法とし、IATAは大きな痛手を受けた。自由化によって、IATAの運賃調整能力は低下しつつある。
●第1の自由
相手国の領域を無着陸で横断飛行する自由
●第2の自由
相手国の領域に、給油等の目的で着陸する自由
●第3の自由
自国領域で積み込んだ貨客を相手国の領域で積み降ろす自由
●第4の自由
自国の領域に向かう貨客を相手国の領域内で積み込む自由
●第5の自由(以遠権)
自国から出発し、相手国の領域で第三国の領域に向かう貨客を積み込み、または第三国の領域で積み込んだ貨客を第三国で積み降ろす自由
●第6の自由
相手国より自国経由で第三国へ行く自由
●第7の自由
相手国から直接第三国へ行く自由
●第8の自由(タグエンド・カボタージュ)
自国から相手国内で貨客を積み降ろし、相手国の国内を運航する自由
●第9の自由(カボタージュ)
相手国の国内を運航する自由
航空市場がいち早く成熟したアメリカは、カーター大統領のもと、航空企業規制廃止法を1978年に成立させた。この法律が規定するのは、中途半端な規制緩和ではなく、規制そのものの廃止である。つまり、国内線において参入規制や料金規制を撤廃した「航空ビッグバン」が起こったのである。
残った規制は反トラスト法のみとなった。こうして、
多くの格安航空会社(LCC:ロー・コスト・キャリア)が参入し、アメリカ国内では、大手航空会社と新たに参入した航空会社によって熾烈な市場競争が繰り広げられるようになった。
一方、国際線においても、アメリカは航空自由化を突き進めていく。1978年、アメリカはオランダ、韓国、ドイツ、ベルギーとモデル航空協定を締結する。そして、1979年にシンガポール、1981年にはタイと結んだ。1992年、アメリカはモデル協定をさらに自由化し、「運賃の自由化」とコード・シェア(共同運航)」を盛り込んだオープンスカイ協定をオランダと締結した。
アメリカ流のオープンスカイは、締結国間であれば政府の介入なしに、航空会社が路線や便数等を自由に決定できる。ただし、第9の自由(カボタージュ)や航空会社の外資規制の撤廃は含まれない。それでもこの自由化により、航空会社は経営の自由度を大幅に高め、収益性の高い路線に参入できるのである。
もともと航空業界は、規制に縛られてきた最たる業種といえる。長らく世界中の国際線が二国間交渉の航空協定に基づいていたことが、それを如実に物語っている。航空会社が他国の空港に路線を開くには、自国の政府を通じて相手国に申し入れ、協定を結んだうえでなければ、路線の運航はできない。たとえば日米なら、乗り入れる空港から航空会社、便数などにいたるまで、両国政府の航空当局が細かい取り決めを結ぶ。すべて政府間の思惑で決まり、指定された以外の空港やエアーラインの就航は認められなかった。
オープンスカイといっても、これまでは米藺、米仏といった具合に、この二国間交渉が基本になってきた。ただし、いったん二国間でオープンスカイ協定が実現すれば、航空会社は相手国の空港に自由に路線を開設できるようになる。そこが違った。
それだけでも画期的な空の自由化なのだが、08年の米国とEUとの協定は、そこからさらに一歩進んだ。米国とEUとの協定のため、原則としてEU内のどこにでも、路線開設が可能になったわけである。
いきおいこの米国とEUのオープンスカイを睨み、空港や航空会社が新しいサービスを展開し始めている。英国最大手の航空会社であるブリティッシュ・エアウェイズ(BA)は、新たに「パリーニューヨーク」「ブリュッセルーニューヨーク」便を開設。従来、BAはヒースローからニューョークに飛んでいただけだが、英国発ではなく、フランスやベルギーから米国向け航空機を飛ばす路線を開設した。これが本格的なオープンスカイ時代の到来といわれる理由だ。
その象徴が英国の政策転換だ。かつて英国は金融ビッグバンの発祥の地といわれ、外資系企業を次々と自国に招き入れた。金融の世界におけるウィンブルドン現象といわれたのは記憶に新しい。
もっとも航空の世界では自由化先進国といわれる米国に比べ、英国は欧州のなかでも、かなり保守的に見られてきた。それが08年になって、一挙に自由化へ転回したのだ。
ウィンブルドン現象と同様、航空の世界でその舞台となったのが、英ヒースロー空港だ。08年、ヒースロー空港は、五つ目のターミナルをオープンした。ショッピングモールには、ティファニーやブルガリといった高級ブランド店が軒を連ね、観光客が殺到した。
折しも、第五ターミナルビルのオープンは、EU(欧州連合)と米国とのオープンスカイ協定の施行とときを同じくしている。ターミナルビル拡張は、オープンスカイ政策に踏み出した英国の姿を象徴していると評判になった。従来のオープンスカイ協定よりさらに一歩進んだ革新的な政策だ、と世界の航空業界の話題をさらったのである。
これを機に、世界中で航空各社の再編が加速していった。08年には、米国三位の規模を誇るデルタ航空と五位のノースウエスト航空が合併を発表。そこから、世界中の大手航空会社の合併観測が、飛びかうようになる。
これらの動きが、オープンスカイによる自由競争の影響なのは間違いないが、そこへ世界不況が再編ブームに拍車をかけている。日本では、ついにJALとANAの合併まで攝かれ、合併後の「JANA」という新社名候補までまことしやかに取り沙汰される始末だ。
欧米における航空自由化の流れは、アジア域内にも波及し、ASEAN諸国の航空輸送も「ひとつの空」に向けて動き始めた。とはいえ、まだまだEUのオープンスカイのように、カボタージュまで自由化されているわけではない。国によって政治的見解や政策が異なるためであろう。
このように世界は、急速に「ひとつの空」を目指して動いているのだ。
さて、日本はどうなのか。2007年に韓国とタイ、2008年にはマカオ、香港、ベトナム、マレーシア、シンガポール、カナダとの間で、乗り入れ地点や便数の制限を廃止し、航空自由化を進めてきた。とはいうものの、現在の航空自由化は、他国の航空機がアメリカに向かうことを条件とする以遠権を認めているにすぎない。
また、自由化といっても、日本の場合は発着枠の制約により首都圏空港は対象外である。
関西空港や中部空港も、その都度交渉しなければならないというレベルでの自由化である。もちろん、カボタージュは認めておらず、外資規制も存在する。欧州域内を除けば、カボタージュ規制や外資規制が存在する国はあるものの、日本の航空自由化は10年遅れ、周回遅れと言われてもしようがない。
この背景には、自国の航空産業を守ろうとする保護主義がある。それでも2006年7月、中国とは旅客輸送量2割増、貨物で倍増、就航可能企業数も倍増する内容で合意し、双方の経済連携を強めた。また2009年には、ついにアメリカともオープンスカイ協定を合意した。
政治的要素が大きく影響する2国間の航空協定では、日本の場合、首都圏空港の限られた発着枠が、相手国への経済的取引の材料となってきた。すなわち、人気のある首都圏空港の発着枠をエサにして、交渉を有利に進めることができるからである。
今後、地方空港の取り巻く環境はますます変化する。その環境の変化に、空港が対応できるかが、地域活性化のカギとなる。
2008年6月、安倍政権のもとでのアジア・ゲートウェイ構想を受けた冬柴プランが発表され、アジア・オープンスカイへ向けての幕開けとなった。これに伴い、地方空港ではこれまでの2国間協定に縛られることなく、自由に定期便が就航できることになった。
ただし、成田空港と羽田空港は発着枠が限界ということを理由に、自由化の対象外とされた。
地方空港の航空自由化により、地方自治体も活発に航空便誘致に取り組んでいる。旅行会社、航空会社への助成、空港使用料の割引、利用促進に向けたフォーラムの開催など、地方自治体は官民をあげて航空需要の喚起に努力している。知事による外国航空会社へのトップセールスも珍しくない。
地元に空港があり、路線があるなら何処へ行くにも、地元空港から直接飛んだ方が速いし安い。特に西日本は韓国や中国に距離的に近く、わざわざ関西空港まで行って乗り継ぐ必要性が乏しくなりつつある。
大韓航空とアシアナ航空は、仁川空港を拠点にして、日本の26空港に就航している。上海空港は日本の17都市と路線を張っている。日本の地方空港のなかには、香港、台北、シンガポールへも就航路線をもっている空港がある。ただし、就航しているのは外国の航空会社ばかりである。
航空自由化の状況下では、航空会社は2国間協定に縛られずに運航できる。航空自由化によって競争が激化すれば、航空会社はより一層の収益を求め、不採算路線からの撤退を加速させる。日本の航空会社が飛んでくれないこともあって、地方自治体は、海外の航空会社への支援やアピールに力を入れることも多い。
日本の航空会社が地方都市=仁川便を就航しないのは、自社便で飛ばしても採算が合わないからである。
地方空港が出発点となるならば、その地方空港に機材整備や搭乗のために人員を配置する必要があり、日本の航空会社にとってはコスト高になってしまうのである。
韓国の航空会社の拠点が仁川空港ならば、仁川空港で整備などの手配をすればよい。日本の航空会社が、羽田空港や成田空港を拠点にして、各地の空港へ飛ばすのと同様に、韓国の航空会社は、韓国の空港を拠点に各地に飛ばすことが経済的なのである。
運賃面では、日本の航空会社は、韓国や中国の航空会社にはかなわない。以前はANAやJALも、小松=ソウル、広島=ソウル、鹿児島=香港、沖縄=香港、広島=グアムなど、随分と地方空港から海外に飛んでいたが、採算が合わないので撤退を余儀なくされた。日本の航空会社のコスト構造が、低価格を期待する顧客層に合わないのである。
さらに、アシアナ航空や大韓航空を利用すれば、日本の地方空港から仁川空港を経由して、アジア諸国や欧米まで、1枚の航空券で行くことができる。当然、仁川空港で再びチェックインする必要もなければ荷物を受け渡しする必要もなく、利便性が高い。
もっとも地方発の国際線は、海外の航空会社の運航だが、JALやANAとの共同運航便が多い。共同運航便とはコード・シェア便とも呼ばれ、1つの定期便に複数の航空会社の便名をつけ、共同で販売する形態である。
航空自由化になった今、地方自治体は、地方空港の活路を国際線に求めるのは当然だろう。
空港を活用することによって、地方自治体はアジアのなかでのポジションを認識できる。地域に空港があるならば、アジアとの結びつきを強化することで、地域経済を活性化できる可能性もあるのだ。
また、国内線においては、地方空港で一定の需要が見込まれる場合には、小型機によって多便化し、潜在需要を喚起することができるかもしれない。というのも、200席程度の中型機では採算は取れなくとも、70席程度の小型機であれば、採算が取れる路線はあるはずだからだ。
フランスでも、シャルル・ド・ゴール空港と国内地方都市はおろか、近隣のEU域内都市を結ぶ路線は縮小傾向にある。日本の新幹線に相当するTGVに需要が奪われているためである。しかし、ローカル・トゥ・ローカルで地方空港と地方空港を結ぶ、小型機によるローカル線は増えているという。
フランスと同様に、東北新幹線や北陸新幹線が開通して小松、青森、富山などの空港は影響を受ける。だが、新幹線よりも低運賃でサービスが提供できれば、安さ目当ての乗客は確保できる。新幹線と航空が競争することで利便性は向上し、運賃は下がる。現に、神戸空港のスカイマークは東海道新幹線よりも低い運賃を設定している。
地方空港にとっては、拠点空港と地方、あるいは地方空港どうし、地方とアジアの都市など様々な可能性がある。地方には地方の個々の事情があり、優先されるべき事項も地方ごとに異なってくる。そうした地方の事情に、霞ヶ関が一律に対応することはできない。
地方は地方の英知と努力によって、責任をもって自分たちの空港を有効に利用しなければならない。それができなければ、廃港もやむを得ない。空港の有効利用は、分権化による地方への権限と責任の移譲、そしてそれらの明確化がカギを握っているのである。
日本の大手航空会社2社が政府の加護を受けている一方で、世界の航空業界は航空自由化のなかで競争力をつけてきた。市場の圧力を政策的に抑制するよりも、市場の流れにいかに乗っていけるかが、航空会社に求められている。
自由化する航空市場の流れのなかで、ヨーロッパやアジアの航空会社と競争しなければならない。日本の大手航空会社は岐路に立たされている。航空自由化の大波は、航空の世界を熾烈な競争に晒し、もはや世界はこれを避けることはできない。それを嘆くのではなくむしろ、この大波をいかに活用して、利用者にとって望ましい航空サービスを実現してゆくかが、世界の航空会社には問われているだろう。
このことは、空港も同様である。中途半端な保護主義は短期的には自国の航空会社と空港を守り、セーフガードとして働くが、長期的には競争力を弱めることになる。航空自由化の大波を、ただただ怖がっている日本であってはならない。そうではなく、航空自由化の利益をうまく享受できるような体制にしてゆくべきであろう。
航空業界が、いかに激しい競争に立ち向かわなくてはいけないかを理解していただけたと思う。かつての国鉄が債務を切り離して国に移管し、地域独占企業のJRとして民営化され、いまやリニア建設まで視野に入れている状況とは、全く違う光景である。
グローバルな競争に晒される航空業界では、自由競争に果敢に挑み、市場の行方を直視して戦略を遂行しなければ生き残れない。国に甘えては生きていけない。
空港も同じである。路線が維持されれば需要が生まれるという考え方は、あまりに短絡的すぎる。需要を喚起するよう、地域の自助努力が当然ながら求められる。航空会社に選ばれる空港にならなければ、存続できない。
この記事を見た人は、合わせて下記の記事も読んでいます!
 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。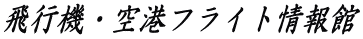
 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。