 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
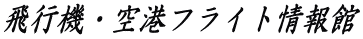
 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
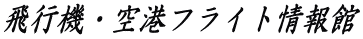
目次
現代のジェット機では、貨物専用機はもちろんのこと旅客機でもさまざまな貨物を旅客と同時に大量に運んでいる。航空輸送の初期の頃の主役は、迅速性を必要とする貨物だった。
郵便がその代表で、当時は郵便機によって空の輸送ルートが開拓されたものだ。続いて旅客機の貨物室を利用して、ある程度のボリュームの貨物を運ぶことが一般化した。でもこの段階までは、貨物の輸送はまだ副次的なものだった。
しかし技術的進歩によって輸送力も増大し、運航コストも下がるようになって、航空貨物輸送のマーケットは急速に拡大した。
現在ではB747Fジャンボを筆頭に貨物専用機が多数使われ、航空貨物輸送専門の航空会社も完全にビジネスとして成立している。
航空貨物は「航空機で輸送される、乗客の手荷物を除く貨物」と定義され、一般にエア・カーゴとかエア・プレートと呼ばれている。当初の航空貨物の中心は、商品サンプル、書類、生鮮食料品だったが、現代は何でも飛行機で運ぶ時代になっており、特に単価が高く付加価値の高いエレクトロニクス製品、IT関連製品や光学機器などは、航空輸送以外考えられないほどになっている。
通常の旅客機の場合には、客室に乗客が乗り、後部や床下の貨物室に乗客の手荷物に加えて、郵便や貨物が搭載されることになる。
この場合は旅客輸送がメインで、貨物輸送はサブのように見えるが、ジャンボのように床下貨物室だけでも、貨物専用のDC-8、1機分に相当する貨物を積めるようになると、これもまた輸送のメインということになる。
貨物専用機(ジャンボではF型)の場合は、客室部分が主貨物室になり、床上、床下ともに貨物を積むことができる。貨客混載機(ジャンボではコンビ型)というのもあって、この場合は客室の前半分に乗客を乗せ、後半分を貨物室として使う。床下はもちろんすべて貨物室だ。
航空貨物の積み方には、バルク・ローディング(ばら積み)、パレット・ローディング、コンテナ・ローディングの3つの方式がある。パレットやコンテナを使う方法をユニット・ローディングという。
最も原始的、歴史的な方式がバルク・ローディングで、貨物はばらのまま積み込まれる。ジャンボでは床下後方の貨物室がばら積み用だ。
貨物専用のジェット機の登場と共に1962年頃から採用されているのが、パレット・ローディングだ。貨物を貨物室の形状に合わせ板で積み上げてネットをかぶせ、パレットと呼ばれるアルミの(当初は合板だった)に固定して、このパレットごと積み込む方式。
航空輸送においても船舶輸送と同様に貨物の扱いを簡素化、効率化するためにコンテナ化が図られ、現在では一般的になっているのがコンテナローディング方式。貨物室の形状に合わせて、アルミ合金や強化プラスチックで独特の形をしたコンテナが作られ使用されている。貨物の多様化に対応して、定型サイズのコンテナ以外に家畜用コンテナ、競争馬用コンテナ、洋服專用のガーメント・コンテナ、魚肉類輸送用コンテナ(マグロ・コンテナとか活魚コンテナ)のようなものも開発されている。
さらにコンテナには入らない、自動車やポートなども飛行機は運ぶ。B767や777は機体の一部が日本でも作られているが、これらやエンジンなども航空貨物として運ばれることが多い。どんなものでも積み込めるように、貨物専用機や貨客混載機では、旅客型よりも大きな側面貨物扉を設けている。
さらにジャンボでは、機首部分をバイザー式にはね上げてそのまま巨大な貨物扉とすることもできる。
現在では航空貨物は多岐にわたっているわけだが、きわめて特殊なものは「特殊貨物」と呼ばれている。
放射性物質(医療用のアイソトープなど)、人工衛星、医療機器などの超精密機械、大型重量物などがこれに当たる。アイソトープなどの輸送では、乗員や乗客、地上作業員の安全も充分に考慮して運ばねばならないから、航空会社では20項目以上の厳しいチェックを輸送前に実施する。
生きた家畜類や生鮮魚介類(台湾からの鰻の空輸などが有名だ)も特殊貨物になる。中国から空輸されたパンダや、生きたシーラカンスのような例もある。特に生きた動物の輸送は環境の管理が大変で、さまざまな対策を工夫している。モナリザやミロのビーナスをはじめとする世界的な美術品の輸送の場合にも、温度や湿度、汚損対策など航空会社は神経を使っている。