 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
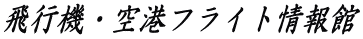
 航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
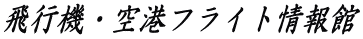
目次
航空機エンジンがその性能を高め始めていた1930年代、自動車用のガソリンのオクタン価(アンチノック性を示す数値)は80程度だった。対して航空機用としてはアンチノック剤として4エチル鉛を添加した87オクタンがアメリカ陸軍航空隊で採用されたのが1930年のこと。
以来、この流れは全世界に波及した。その後、航空ガソリンは1930年代を通じて92オクタン、98オクタンとその規格を高めていった。これはより高いオクタン価を要求していた過給エンジンが主流となっていったことが理由である。
オクタン価については各国の石油精製事情によって微妙に異なっていたが、実際のところその性能はどんなエンジンと組み合わせるかで微妙に異なっていたため、数字の違いに起因する性能差については一概には評価できなかった。
そして1938年、アメリカ陸軍航空隊では最初の100オクタン規格が登場する。同じ頃、イギリスではとくに高過給エンジンにおいて、巡航時にスロットルを絞ったリーン燃焼時と、スロットル全開フルブーストといったオーバーリッチ燃焼時では、アンチノック性が大幅に異なることが確認されたため、まずイギリスでオクタン価の並記が始まることとなった。これが「80/87」、「91/98」、「100/130」であり、小さい方の数字はリーン時、大きい方の数字はオーバーリッチ時のオクタン価を表したものだった。
ここで注意しなければいけないのは、オクタン価100のイソオクタンをその基準としていたオクタン価表記においては100が最高価であり、それ以上は存在しなかったということだ。では130とはどういう意味かというと、正確にはオクタン価ではなくP/N(パフォーマンス・ナンバー)と呼ばれていた数字であり、100に対して130は30%ブースト圧を上げることが可能という意味だった。
1944年、アメリカとイギリスにおいて「115/145」が最高規格ガソリンとして登場し高過給エンジンの信頼性はさらに向上することとなった。この時点において日本やドイツといった枢軸国側の航空ガソリンは、依然として最高規格が98オクタン程度であり、それも非常に限られた量しか供給されなかった。
わが日本の場合だと91オクタン以上の高規格航空ガソリンは最後まで国内で大量生産できず、開戦直後に占領したボルネオの油田地帯に残されていた精製設備を復旧した上で、現地生産したものをタンカーで国内に輸送していた。国内の高規格ガソリン精製施設は三重県鈴鹿に建設していたが、空襲の影響で結局完成しなかった。
航空エンジンには潤滑油(エンジンオイル)も必要だが、こちらは初期から植物油が重宝されていた。意外にも、じつは初期の内燃機関の潤滑油としてはトウゴマの種からとる「ひまし油」が最も適していたのである。その耐熱性と潤滑性は圧倒的であり、精製技術が未熟だった頃の鉱物油などはまったく及ばなかった。
2.
しかし、ひまし油には致命的な欠点があった。それは酸化が早く安定した性能を発揮できる期間が極めて短かったこと。そして寒冷地では固化してしまうことである。ひまし油は初期のプリミティブな潤滑構造しか備えていなかった航空エンジンに信頼性をプラスする上で大きな役割を果たした一方、鉱物油の精製技術が高まり、さらに各種添加剤が開発されると、その性能は逆転。1940年前後には多くの国で鉱物油への転換が図られ、第二次世界大戦末期には新たに化学合成油の開発へと移ることとなった。
余談ながらわが日本陸海軍航空隊においては陸軍航空隊の方が早く植物油から鉱物油へとスイッチしながらも、太平洋戦争中に鉱物油の性能不足が改めて指摘されたことから一部で植物油へと戻っている。一方海軍航空隊の方は1940年代初めに鉱物油へとスイッチしてからは一貫して鉱物油を使用していた。ちなみに陸海軍共に第一線機に使用していたのは太平洋戦争勃発前に大量に輸入備蓄していたアメリカ製であり、現場で潤滑油のことを「モービル油」などと呼んでいたのはそのブランドに由来する。